風と共に去りぬの感想・考察(ネタバレ有)
ここからは、本作に関する考察を含めた感想を述べていきたいと思います。なお、記事の構成上多くのネタバレを含みますので、その点はご了承ください。
南北戦争を舞台に作者が描きたかったのは「南部への賛美」である
1900年生まれのミッチェルは、母方の親戚から南北戦争について聞かされて育ちました。彼女は後年、「持てる知識の全てを本作に注いだ」と語っているほど。
戦争のきっかけとなった黒人奴隷の存在。これは言ってしまえば「人種差別」ということになるわけですが、先にも説明したように本作は南部視点の物語ですから、黒人の使用人は作中で「古き良き時代の象徴」として描かれています。
がしかし、ミッチェルが描きたかったことは決して人種差別を中心とした部分ではなく、過ぎ去った優雅であった時代や美しい大地を持つ南部への賛美であるのだと思います。
オハラ家三代にわたっての乳母である黒人奴隷のマミーと、スカーレットの関係性は印象的です。マミーはスカーレットに進言できる数少ない人物で、そこには信頼があります。
マミーは北部の勝利で奴隷が解放された後もオハラ家に残るのですが、他の解放奴隷に対して嫌悪感を抱いている描写があります。
そこからは、自身がスカーレットやオハラ家に必要とされている不可欠な存在であるいう自負が見えてきます。が、ミッチェルは彼ら黒人の視点で物語を語っていませんので、この部分に関しては様々な解釈が出来ると思います。
一方、黒人メイドのディルシーもオハラ家当主(スカーレットの父)に恩義を抱いています。それは役立たない虚言癖のある娘と共に「買ってもらえた」ためなのですが、これには「南部の農園を美化しようとして体良く描かれているな」という印象を否めないのも事実。
実際、本作では「私は白人様に買ってもらえて幸せです」と言ってしまっているワケですから、是非はともかく批判の声が上がる理由はよく分かります。
ヒロイン・スカーレットの魅力は底知れぬ生命力と故郷への愛
スカーレットという女性は、当時のアメリカで一般的だった女性像とは随分とかけ離れています。鼻っ柱が強く、度胸があり、ヒステリックで我がままな側面があるスカーレット。それゆえ、レットからはオポチュニスト(御都合主義者)とも評されています。
スカーレットの故郷・タラは架空の地ですが、ミッチェルは当時の南部をイメージしてタラを描きました。スカーレットにとっては何をさて置いても大切な場所で、彼女は文字通りタラのために生きます。
彼女がやってのけたことは、
・タラにかかる税金を工面するための愛のない結婚(それも妹スエレンの婚約者)
・農園主のお嬢様であるにも関わらず、生活費のため手荒れや日焼けが酷くなるほどに綿花摘みをする
・内働きの奴隷にすら断られた野良仕事を率先してする
・強盗に押し入ってきた北軍の脱走兵を銃殺する
など数知れず。実際、スエレンは「私はそんな畑仕事など奴隷と同じことは出来ない」と言い張っています。もっとも、戦争勃発まで家事や畑仕事とは無縁だったのはスカーレットも同じなのですが。
スカーレットは食料と衣類が不足して苦しむなか、妻の死で気が触れた父や妹達・メラニー・子ども・召使いたちにとって「自分がだけが頼りになる存在なんだ」と気づきます。
同時に、
神様が証人だわ。神様を証人にしてあたしは誓う。あたしはヤンキー(北軍)なんかに屈しない。どこまでも生き抜いてみせる。そして戦争が終わったら、もう二度とひもじい思いなんかしない。そうだ、うちの人にだって、絶対にそんな思いをさせない。よしんば、そのために盗んだり人殺しまでしなければならないとしてもーー。神様を証人にして、二度とひもじい思いなんかするものか
と決意するのです。
戦争を体験した者にしか理解できない飢えの苦しみ、生きることへの執着心が強く現れている印象深い一節です。
責任感を持ち、こんなにもタラのために奮闘しているスカーレット。しかしながら、親戚や近所の女性たちからは心良く思われていません。なぜなら当時の価値観では、女性は「慎み深く」なくてはならないから。
戦争が終わりタラを出てからも、お金を稼ぐこと、ましてや自ら会社を経営するスカーレットは異色の存在でしかなかったのでしょう。が、スカーレットは守るべきものが分かっている聡明な女性ですから、「周りに何と言われてもいいわ!」と考えているのです。
彼女の真の理解者はメラニーとレット、そして読者だけでしょう。特にメラニーとスカーレットとは、相反する性格のようでいて根本のところでは密接に結びついている、言わば表裏一体とも言える関係だと思います。実際ミッチェルはメラニーを「本当のヒロイン」と呼んでいました。
スカーレットは読者にも勘違いされうやすい人物なのですが、誰よりもタラと家族を守りたいと考えている愛情深い人物といえるでしょう。
人種や性で差別されることがなくなったとは言い難い1930年代、ミッチェルはそれらが顕著であった南北戦争を舞台に、男性に負けないようたくましく生きるスカーレットの姿を描きあげたことは非常に興味深いです。
人権意識が現代にそぐわないという側面がある一方で、社会で活躍する女性を描く「フェミニズム」を強く押し出した作品ともいえるかもしれません。
似た者同士のスカーレットとレット・バトラーとのロマンスに注目したい
スカーレットは「アシュレを愛してる」と言いますが、果たしてその想いは真実だったのでしょうか。私は、欲しくても手に入らなかったものに対しての「執着」がそう言わせたのではないかと感じます。
アシュレは後世の文献やファンの間でも「夢見がちで意気地なし」と評価されることが多い人物なのですが、私はひどい現実主義者だという印象を受けました。
しかしスカーレットのように対処能力に長けているわけでないので、商才もなく上手く立ち回れないアシュレをスカーレットは守り続け、それを愛と信じていたのではないかと考えます。
対するレットは、スカーレットと似たもの同士で自己中心的な野心家。「僕の内部にもきみと同じ性質がある」と語り、出会った時からスカーレットに惹かれています。
弱みを見せることを嫌うスカーレットが、カーテンを使って新調したドレスでお金を借りにくるというプライド高いところや、その向こう見ずな性格すらも愛しく思っていたでしょう。
が、レットはスカーレットにその情熱を伝えてはいけないと悟っていました。想いの半分も正直に伝えずにいたわけですが、レットからは隠しきれないスカーレットへの愛が垣間見えます。
スカーレットはレットを嫌い続けました。が、いざという時に頼れるのがレットであることは理解しています。レットは後にスカーレットのことを「苦労を知らない少女のままで居させてあげたかった」と語っていますが、戦争が彼女を変えてしまったのでしょう。
レットはスカーレットとの娘ボニーを溺愛し我がままに育てるのですが、スカーレットに与えたかった愛情の全てをボニーに向けたのだという印象をもちます。スカーレットもレットも素直になって話し合えば…。読者としては何度そう思ったことでしょうか。
レットとスカーレットはその激しい性格ゆえににすれ違いばかりですが、二人のロマンスは本作の見所であるといえましょう。
心に響く名言が多い!
本作からは心に残る名場面、名言がたくさん生まれています。その中でも特に有名で、かつ全てを失って一人きりになったスカーレットの不屈の精神が分かる一節をご紹介します。
みんな、明日、タラで考えることにしよう。そうすれば、なんとか耐えられるだろう。明日、レットを取り戻すことを考えよう。明日はまた明日の陽が照るのだ
最後の部分は原文だと「tomorrow is another day」となっているので、直訳すると「明日はまた違う日になるのだから」といったところ。実はこれ、聖書の言葉なのです。
スカーレットの母は敬虔なクリスチャンで、父はアイルランド系の移民であり土地を大切に生きてきました。スカーレットの精神だけでなく、脈々と受け継がれるオハラ家の気質のようなものを感じられる一節と言えましょう。
まとめ
『風と共に去りぬ』という作品は如何でしたでしょうか。確かに本作が「問題作」といわれる要素を含んだ作品であることは認めましょう。
ですが、一方で「奴隷制度や黒人差別が肯定されていた作品を抹消することで、間違いなく過去にあった『歴史』を丸ごと抹消してもいいのか」というのも、私たちが考えなければならない問題なのではないでしょうか。
スカーレットには感情を揺さぶられますし、レット・バトラーとのロマンスも感動的。さらに母・エレンや妹・スエレンなど脇役のエピソードも深く掘り下げて描かれており、登場人物がリアルに感じられる作品です。
昨今はあまり好ましくない形で名前が挙がりがちな本作ですが、あらすじを知らない方だけでなく、映画は見たけれど原作は読んだことがない、という方にも一度読んでいただきたいと思える作品です。
【参考文献】
・風と共に去りぬ 1〜5 (大久保康雄 竹内道之助 訳、新潮文庫、2004年版)
・謎解き『風と共に去りぬ』(鴻巣友季子著、新潮文庫、2018年)
・高度成長期に愛された本たち (藤井淑禎著、岩波書店、2009年)
【参考ウェブサイト】
・南北戦争 (Wikipedia)

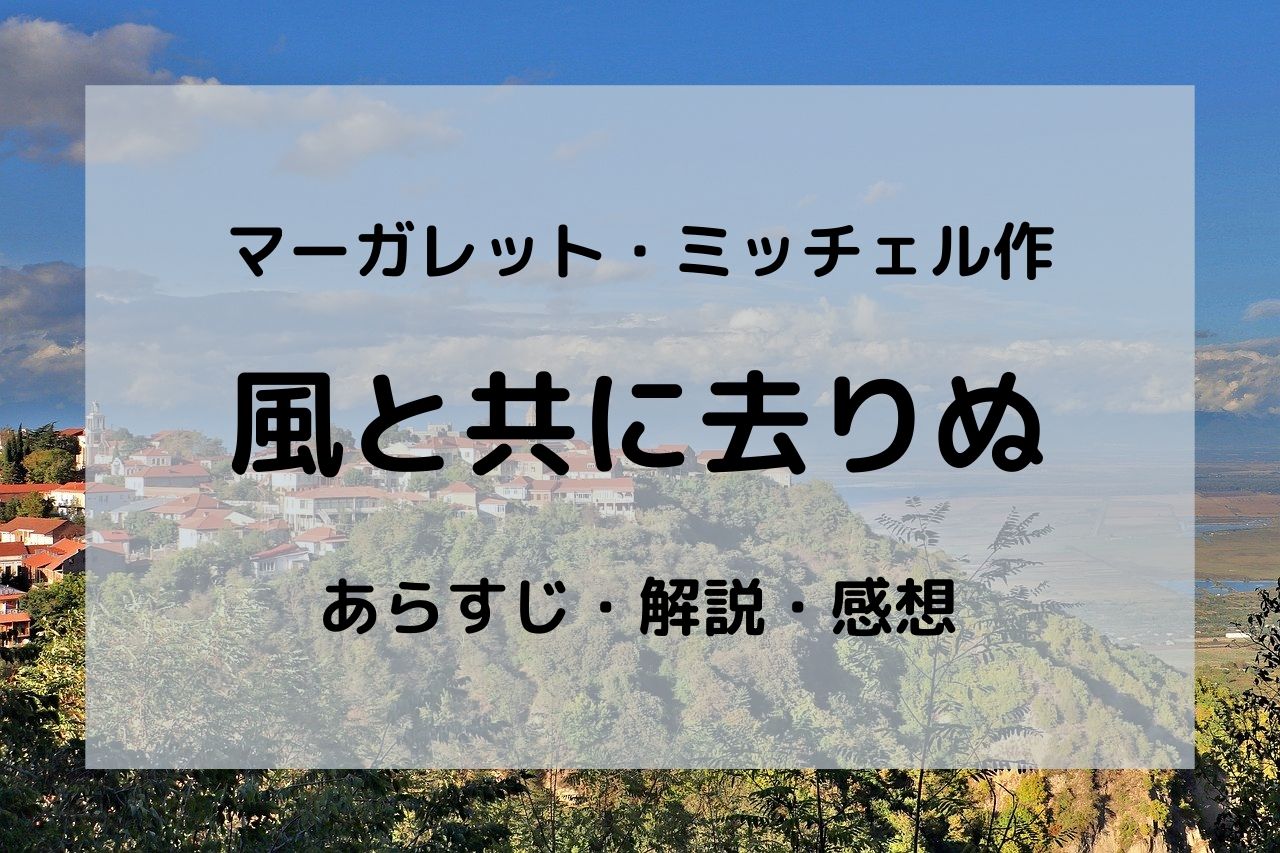


コメント