『ノルウェイの森』を愛する理由
 出典:Amazon
出典:Amazon
ここまでの指摘から『ノルウェイの森』という小説のストーリーには問題が多いということが分かっていただけたのではないでしょうか。
つまり、いわゆる「大衆文学」に求められるようなストーリーは存在せず、純粋な純文学作品としての作風が展開されているのです。
これが、この本が大衆ウケしない最大の要因なのではないでしょうか。
あまりにもベストセラーになってしまったために、直木賞を取るような「大衆文学」としての小説を期待してこの本を読んでいる人が多いように感じます。
そもそも村上春樹は純文学を専門にしているので、世界観や緻密なストーリーだけで読み手を魅了するタイプの作家ではないのです。
もっとも、純文学作家の中でもストーリーだけ見れば万人ウケしない方だとは思いますが。
つまり、『ノルウェイの森』の優れたところは、そうした部分ではないのです。そのため、映画化や舞台化が全くハマらない作品ともいえるでしょう。
ぜひ、そうしたものではなく、実際に小説を読んでみてほしいところです。
そして、ここからは私が考える「愛すべき理由」を紹介していきます。
登場人物たちの個性や思考が魅力的
まず、登場するキャラクターたちの個性と思考に魅力があると感じています。
「私」の主体性がなく、世間に反発心を覚えるも流されるままに精神をすり減らすところも、直子の壊れそうで不安定なところも、緑のはつらつとしているがどこか達観しているところも。
他にも登場人物は何人もいますが、その誰もが少し世間からズレています。
そうした「ズレ」を内包しつつも、どこか達観した価値観をもっているところに、私は共感を覚えます。
私も比較的物事を冷たく考えるほうなので、登場人物たちのどこか冷めている心の底の部分にたまらない魅力を感じるのです。
つまり、言ってしまえば私は村上春樹のことが好きなんでしょう。
小説の登場人物というのは、著者の価値観を反映するものです。その人物たちに魅力を感じている以上、これは否定できません。
平坦で冗長ながらも不思議と惹かれる文章
次に、この本の文章にも魅力があると感じています。
もともと村上春樹の文章は基本的に好きなのですが、この本特有のどこか暗くて閉塞感が漂う雰囲気と、彼の文体の相性は最高だと思います。
決して簡潔な文章ではありませんし、力強さを感じる文章でもありません。
それでも、いやむしろそれだからこそこの本の文章がたまらなく好きなのでしょう。
これは私の昔からの好みなのですが、完璧なものはあまり好きではありませんし、どうも半官贔屓的な考え方をする傾向にあります。
「完璧」な文章に惹かれない理由
私が思う「完璧な」文章を書く作家は、三島由紀夫です。
三島文学は、文体が力強く気高く、神々しささえ感じられます。芸術作品でいえば、均整の取れた彫刻といったところでしょう。
ただし、完璧だと評価する一方、決して三島文学が好きではありません。その理由は単純で、あまりにも隙がなさすぎるからです。
より分かりやすいところで例えるならば、「何もかも完璧な女を好きになるか」
という問いに変換してみると分かりやすいのではないでしょうか。
容姿端麗・文武両道・品行方正で、それを自覚しているとしましょう。
ものすごく魅力的な要素がそろっている一方で、私はどこか物足りないように感じます。
また、これは三島特有のものですが、素晴らしい文章を書く自分自身を愛する気持ちが文章に表れすぎているきらいがあります。
物書きは誰しもナルシストだとは思いますが、三島の場合はちょっとそれが強すぎます。
「隙だらけ」な村上春樹の文章
一方で先ほども触れたように、村上春樹の文章には数多くの隙があります。盛り上がりに欠ける文体で平坦ですし、一見冗長な表現もなくはありません。
しかし、こうしたある種の平坦さや冗長さは、彼独特の言葉選びや比喩のセンスによって魅力的に仕上げられ、「村上ワールド」を生み出してしまうのです。
彼の作品には、全体的にじんわりと沁みるような良さを感じます。
女性に例えると、容姿は平凡で文武も特に秀でたところはない。けれどもものすごく笑顔が可愛いというようなものでしょうか。
すると、今まで平凡で特に気にもならなかった彼女の平凡な点が、むしろたまらなく愛おしく感じられる気持ちが、なんとなくわかってもらえるように感じます。
ひとたびそう感じると、「あばたもえくぼ」にしか感じられなくなっていきますし、こうして無数のハルキストは生まれたのでしょうね。
「死は生の一部である」という死生観
さらに、この本特有の死生観も、私にとっては共感できる点が多いです。
この本では、かなり多くの人間が自ら命を絶ちます。キズキ・直子・直子の姉・ハツミさんなど。
そんな彼らの「死」の描き方と、周囲の受け入れ方が非常に好きです。
ここでは、作品の「裏の主役」といっても過言ではない「キズキ」という人物を例にしてみましょう。
直子と「私」にとってのキズキ
彼は、直子と「私」の学生時代の親友でした。しかし、ある日突然自宅で自殺を図り、そのまま帰らぬ人になります。
その死は、「私」の視点では突然のものでした。快活で裕福で、知り合いの少なかった「私」にも親しくしてくれたキズキ。
このように、非常に死を淡泊に描くところが特徴的で、そこに共感を覚えました。
しかし、直子には思い当たる節があったのではないかと思います。彼らは付き合っていて、「私」がいないところではキズキが別人のようでもあったと告げています。
物語内ではこれ以上のことは分かりませんが、キズキの死は直子の時を止めてしまったのではないかと思うのです。
それ以降、直子と「私」は「生きながら死んでいる」状態になっていきました。そうして精神をすり減らし続けていた二人が再会し、関係をもつようになります。
結局、直子は「私」の中にキズキを見ていたのでしょう。
こうして代償行為を続けていた直子でしたが、やがて精神が限界を迎え、キズキの後を追うように自殺してしまいます。
一方の「私」は、直子とキズキを失いながらも生き続けていくことになります。ハツミさんを失った永沢君という「私」の先輩も生き続けていました。
つまり、「死は生の一部である」というエピグラフは、村上春樹なりの「死」という出来事に対する答えなのでしょう。
失ったものとともに失われていく直子と、そうではない「私」。
この対比構造で描かれる「死」は、儚くもとても美しく感じられました。
まとめ
ここまで、『ノルウェイの森』について色々と書いてきましたが、いかがだったでしょうか。
決して完璧な小説ではありませんが、それがたまらなく愛おしい小説だと思います。
また、先ほど「ハルキストではない」と宣言したように、基本的に村上春樹の「異世界もの」にはあまり興味がありません。
好きなのは鼠四部作やこの本、それと短編集くらいでしょうか。
他の本はそもそも設定に惹かれないので手を出していませんが、いつかは読んでみたいと思っています。
ただ、村上春樹自身が「この本は実験的」といっているように、後の作品がこの本を超えてくるとは思えないんですよね。
20代後半~30代前半という、精神の活力と不安定さが交差している時期に生まれた本だからこそ、という意味があるようにも感じますし。
たぶんそれ以上の年になってしまうと、もうこういった小説は書けないように思えます。なんとなくですが。


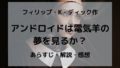

コメント