アンドロイドは電気羊の夢を見るか?の感想・考察(ネタバレ有)
リックの悩みは「自分がアンドロイドかどうか」がメインではない
P・K・ディックがよく取り扱うテーマに、「ほんもの/にせもの」があります。
これは「ほんもの」と「にせもの」の区別がつかなくなってしまうこと。さらには、「にせもの」が「ほんもの」よりほんものらしくなってしまうこと。
(ディックの『記憶売ります』を原作にした映画『トータル・リコール』をご覧になったかたはわかりやすいかもしれません)
本作でも、人間そっくりのアンドロイドと、それを追う人間の区別がつかなくなりかける描写があります。
リックは「自分もまたアンドロイドで、人間だった擬似記憶を植え付けられているのではないか」と、物語の途中で疑います。(実際、映画『ブレードランナー』ではこの点にフォーカスがあてられていました)
しかし、本作においては、「ほんもの/にせもの」の間に一線が引かれています。
作中、人間かアンドロイドかを判断するために、「フォークト=カンプフ検査」という小道具が使われます。
検査では命に関する質問(「誕生日の贈り物に、仔牛皮の紙入れをもらった」など)を投げかけ、反応を測って人間とアンドロイドを見分けます。
アンドロイドはこの動物に関する質問に反応が遅れるため、ここから判断が可能なのです。
実際、リックは「アンドロイドは感情移入ができない」と独白します。プリスたちアンドロイドの言動にも、動物への感情移入ができないことが明記されています。
これが、後述する共感(エンパシー)ボックスを使えないということにつながります。
なので、「自分がアンドロイドかどうか?」という疑問は、リックの大きな悩みではありません。結局、自分がそうでないことは道具で分かるから。
では、リックは何に悩むのでしょうか?
人間とは「自分以外の何かに感情移入ができる」存在
リックを悩ませた最大の思いは、「自分が、アンドロイドに感情移入してしまったこと」です。
物語の最初に、リックはレイチェル・ローゼンという少女に出会います。
彼女はアンドロイド製造会社の一族のひとり、という触れ込みで姿を見せます。が、実際には人間の記憶を埋め込まれたアンドロイドでした。
リックは、このレイチェルに魅力を覚えます。
そして、狩りのさなか、いつの間にか獲物であるはずのアンドロイドに感情移入してしまっている自分に気付くのです。
さきほど書いた、「自分がアンドロイドではないか?」という疑いは、ここで生じました。
しかし、一方でリックは間違いなく人間。彼の悩みは、バウンティ・ハンターが処分する相手に感情移入してしまっていることなのです。(「処分」ということは「殺す」ということになってしまいます)
感情移入ができるのは人間であるということ。つまり、人間であるために、リックは悩むわけです。そのどうしようもない悲しみが、この作品に単なる娯楽以上の深さを与えています。
「人間とはなにか?」について追求した小説と言いかえることも出来るでしょう。
作中で示されている人間の定義とは、「感情移入を、他の何かにできる存在」というもの。
その何かとは、人間であり、動物であり、アンドロイドであったりします。
リックは妻・イーランの鬱状態に悩まされながらも、ところどころで彼女を思います。また、生きた山羊を手に入れたときは、幸福に満たされます。レイチェルに対しては、恋愛なのかどうか迷いつつ、心を惹かれます。
共通して言えるのは、「相手に対して、自分の心を動かす」ということです。それが憎しみなのか、愛なのかは関係ありません。
自分の心が、相手に反応すること。その反応自体が、人間の証であるとも言えるでしょうか。
本作においては、その反応が、とくに「相手へ尽くす」ということにあらわされています。
孤独な青年であるジョン・イジドアは、プリスたちがアンドロイドと知っても、彼女たちに尽くそうとします。
その結果はお読みになればわかると思いますが、彼がひたすら尽くす姿は崇高でさえあります。
そして、「人間とはなにか?」という問いに、イジドアの姿を通して、ひとつの答えを出していると思われるのです。
共感ボックスの存在は、現代SNS社会を言い当てている?
ここで、先ほど少し触れた「共感(エンパシー)ボックス」について説明しておきましょう。
共感ボックスとは、「黒い箱と、ブラウン管と、二つのハンドル」からなる機械。
ハンドルを握ることで、人はウィルバー・マーサーという老聖人と魂をつなげることができるのです。
マーサーは荒野の坂道をひたすら登っており、時おり邪悪な者たちから石つぶてを投げつけられます。
その痛みや苦しみは、ハンドルを握っている人間にも伝わってきます。
ボックスにつながることで、マーサーの苦悩だけでなく、ボックスを介するすべての人間の苦しみ・喜びを、皆でわかちあうことが可能となるのです。
これは作中で、「マーサー教」と呼ばれ、衰退した人類を支える大きな柱になっています。この「つながり」によって救いを見出そうとする姿勢は、現実を生きる私たちが日々触れている「インターネット社会」と共通したものがあるかもしれません。
もちろん、今のところ現実世界は滅亡に瀕してはいません。しかしながら、これまで人類が依存してきた「権威」的なもの(例えば神、主義…)を、わたしたちは失いつつあります。
その孤独から逃れるように、「つながる」ということを求めるのは、SNSなどの流行にも表れているのではないでしょうか。もちろん、共感(エンパシー)ボックスと、SNSが完全に同じ物だとはいいません。
まず、共感ボックスには、マーサーという絶対的な超越者がいます。対して、私たちの世界のネットには、中心というものがありません。
しかし、共感ボックスにつながっている人びとは、苦痛や喜びもわかちあうことができる、という点には注目すべきです。
共感ボックスの存在が示す「横のつながり」という構造自体は、そのままネット社会の予見と言ってしまってもいいのではないでしょうか。
「共感」という感情と、それを可能にするネットワーク。
このテーマに注目するだけでも、本作は「今、ここにいる、『わたしたち』にとって必要な小説である」と言えるでしょう。
ウィルバー・マーサーは、つねに「わたし」に寄り添うのです。
まとめ
『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』はSFを越えて、人の心に訴えかける小説。人生の困難に出会ったとき、そっと寄り添ってくれる作品と言えるかもしれません。
21世紀のいまだからこそ、読まれる価値のある「未来の話」です。ぜひご一読を。

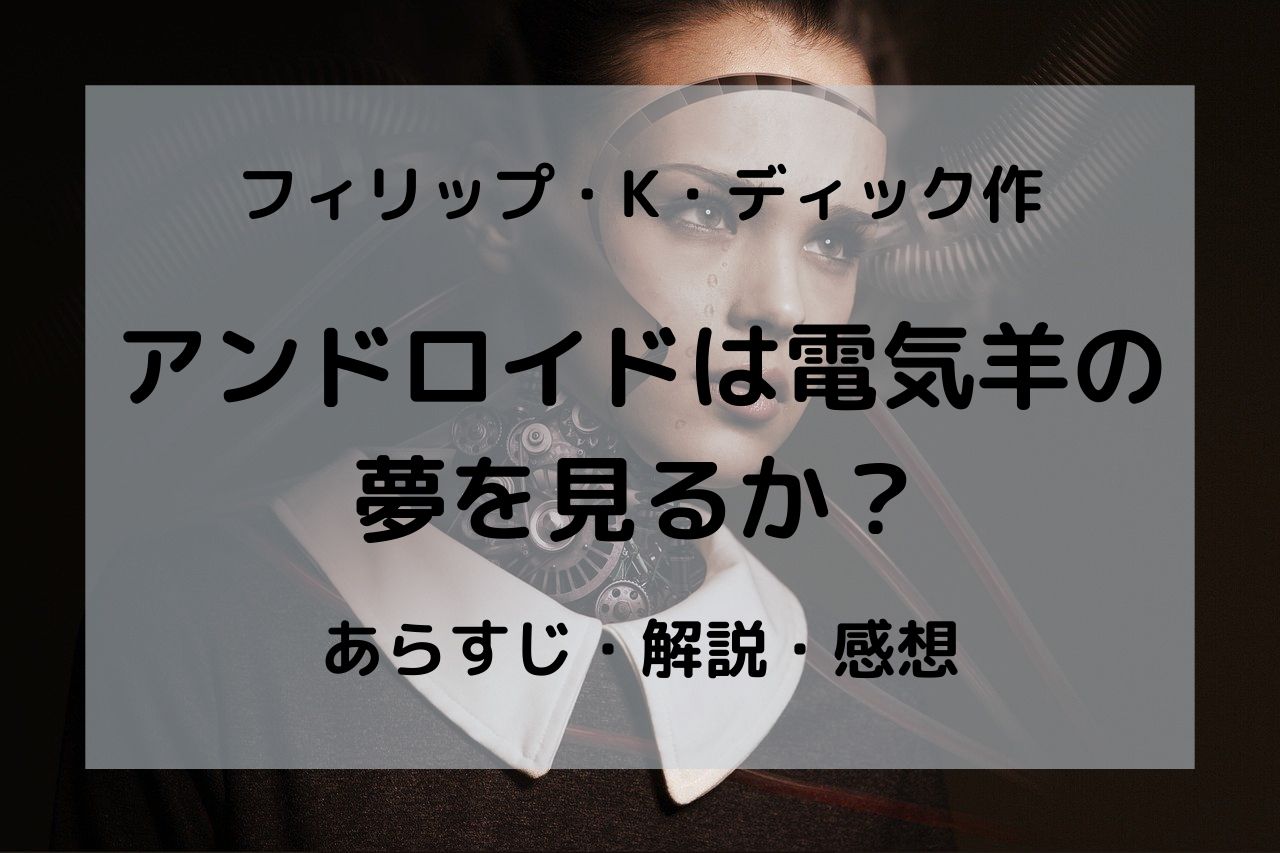


コメント